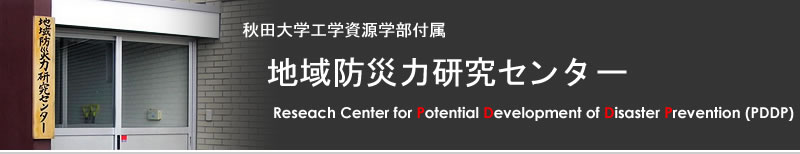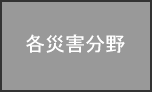秋田県は830年天長地震,1694年能代地震,1896年陸羽地震,1914年強首地震といった地震災害を数多く経験しています.また,秋田県内には北由利断層を始めとする多く
の活断層があり,地震災害ポテンシャルが高いところです.
地震災害は,広く捉えれば,地盤災害,斜面災害,津波災害,建築物や諸施設の被害といった災害などを含みます.しかし,本センターでは上述のように細分化し,地震災
害分野では主に岩盤の破壊,地震発生域のテクトニクスといった地学的なことを対象とします.
地震災害では地質や地盤が関係し,これらの特性評価が重要です.地盤の液状化や土木構造物の被災は我々の日常生活に大きな影響を及ぼします.これらの問題にも将来的には対応できるようにしたいと考えています.
|