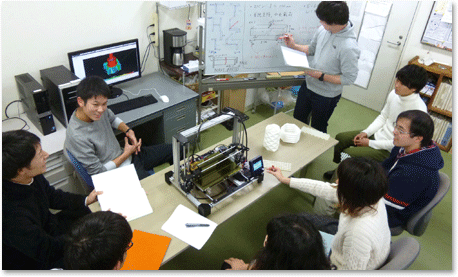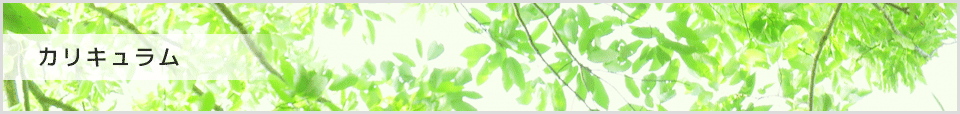
カリキュラムとその特徴
社会基盤コースでは、土木工学のベースである構造力学、水理学、土質工学、都市・交通工学、コンクリート工学などを主体とした基礎力をしっかりと身につけ、環境に配慮し防災・減災機能を有した社会基礎を整備する知識を修得していきます。さらに高齢者も快適に生活できる都市基盤の整備や積雪寒冷地においても安全で持続可能な社会基盤の構築に対して、優れた問題解決能力を発揮できる人材の育成を目指しています。
社会基盤コースの学習・教育到達目標
1.社会基盤コースの学生が習得すべき能力と素養(学習・教育到達目標)
社会基盤整備において、人間の幸福や公共の福祉、地球環境的視点から、社会の要請を多面的にとらえ、確固とした土木環境工学の基礎的および専門的知識や技術を用いて、総合的な解決策をデザインする素養と能力を身につける。
◎土木環境工学の基礎知識◎土木環境工学の応用知識◎社会基盤整備における総合的な解決策のデザイン能力
2.そのための素養としては、
自然や生命等、地球環境に広く関心を持ち、これを多面的な視点で考察する能力、ならびに土木環境工学に関する基礎知識の応用を通じて、自然と社会との関わりやそれら相互の影響を理解し、技術者として自然や社会に対する責任を自覚する要素を身につける。社会が抱える課題の進化を認識し、土木環境工学において新たに生じる課題対応に必要な専門知識や技術を、自主的、継続的に学習できる能力を身につける。
◎地球環境に関心を持ち多面的な視点で考察する能力◎技術者としての倫理観◎新たな課題に対応できるよう自主的・継続的に学習する能力
3.そのための知識としては、
数学や自然科学、情報技術などの基礎知識を習得し、自然現象や社会現象のメカニズムを理解する能力を身につける。また、人文科学や社会科学の知識を習得することで、多様な情報を収集・分析し、社会の要請を多面的にとらえる能力を身につける。
◎自然科学などの基礎知識◎人文科学および社会科学知識◎情報を収集・分析する能力
4.そのための技術(スキル)としては、
現象を理解し、問題の所在・解決策を論理的に記述・発表する能力を身につける。また、討論を通じて現象に対する理解を深め、解決策の問題点を改善する能力を身につける。さらに、国際的に通用するコミュニケーション基礎能力を身につける。自然環境、社会環境、経済環境、時間等の制約下において、目標とそこに至るプロセスを自ら設定し、計画的に仕事を遂行する能力を身につける。
◎論理的に記述・発表する能力◎討論を通じて改善する能力◎国際的コミュニケーションのための基礎能力◎目標とプロセスの設定能力◎計画的な仕事の遂行能力
| 1年次 | 2年次 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | ||
|
教 育 基 礎 教 育 科 目 |
教 養教 育 |
初年次ゼミⅠ 1つの外国語 |
初年次ゼミⅡ データサイエンスリテラシー概論 主題別科目・スポーツ文化科目 英語Certificate/日本語Certificate 1つの外国語 |
1つの外国語 | 主題別科目・スポーツ文化科目 1つの外国語 |
1つの外国語 | 1つの外国語 | ||
|
基 礎 教 育 |
基礎線形代数Ⅰ 基礎微分積分学Ⅰ 基礎力学Ⅰ 基礎英語 化学系選択科目 |
基礎線形代数Ⅱ 基礎微分積分学Ⅱ 基礎力学Ⅱ 化学系選択科目 |
基礎線形代数Ⅲ 基礎微分積分学Ⅲ 基礎電磁気学Ⅰ 化学系選択科目 |
基礎線形代数Ⅳ 基礎微分積分学Ⅳ 基礎電磁気学Ⅱ 基礎物理学実験 基礎情報学 基礎AI学 化学系選択科目 |
多変数微分積分学Ⅰ | 多変数微分積分学Ⅱ | |||
|
専 門 科 目 |
グリーン社会システム概論Ⅰ | グリーン社会システム概論Ⅱ | 基礎数値解析実習 グリーンITを支えるエレクトロニクスと材料 材料力学Ⅰ 流体力学Ⅰ 金属材料学Ⅰ 電気回路学Ⅰ 応用解析学Ⅰ |
基礎数値解析実習 材料力学Ⅱ 流体力学Ⅱ 金属材料学Ⅱ 電気回路学Ⅱ 応用解析学Ⅱ 地球の環境 |
環境と健康を支える生物学 Introduction to Engineering for Social Systems Ⅰ 構造力学Ⅰ 水理学Ⅰ 土質力学Ⅰ 社会計画数理Ⅰ 建設材料学Ⅰ 測量学Ⅰ 社会基盤学セミナー 土質力学演習 社会資本整備の歴史 |
Introduction to Engineering for Social Systems Ⅱ 持続可能な社会を支える化学 構造力学Ⅱ 水理学Ⅱ 土質力学Ⅱ 社会計画数理Ⅱ 建設材料学Ⅱ 測量学Ⅱ 社会基盤学セミナー 土質力学演習 国土計画と地域開発 |
|||
| 3年次 | 4年次 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | ||
|
教 育 基 礎 教 育 科 目 |
教 養教 育 |
||||||||
|
基 礎 教 育 |
|||||||||
|
専 門 科 目 |
データサイエンス 構造力学Ⅲ 水理学Ⅲ 地盤工学Ⅰ 都市システム計画Ⅰ 交通システム計画Ⅰ コンクリート構造工学Ⅰ 測量実習 社会基盤学実験 地盤工学演習 福祉のまちづくりⅠ 建設材料学Ⅲ 衛生工学Ⅰ 社会基盤学特別講義 |
データサイエンス 構造力学Ⅳ 水理学Ⅳ 地盤工学Ⅱ 都市システム計画Ⅱ 交通システム計画Ⅱ コンクリート構造工学Ⅱ 測量実習 社会基盤学実験 地盤工学演習 福祉のまちづくりⅡ 建設材料学Ⅳ 衛生工学Ⅱ 社会基盤学特別講義 |
機械学習 海岸海洋工学Ⅰ 測量実習 鋼構造設計学Ⅰ マトリクス構造解析Ⅰ 環境水理学Ⅰ 河川工学Ⅰ 地盤防災工学Ⅰ 高齢者・障害者の交通計画Ⅰ 交通施設工学Ⅰ 都市・交通計画演習 コンクリート構造工学Ⅲ 社会基盤学特別講義 火薬学 |
機械学習 海岸海洋工学Ⅱ 測量実習 鋼構造設計学Ⅱ マトリクス構造解析Ⅱ 環境水理学Ⅱ 河川工学Ⅱ 地盤防災工学Ⅱ 高齢者・障害者の交通計画Ⅱ 交通施設工学Ⅱ 都市・交通計画演習 コンクリート構造工学Ⅳ 社会基盤学特別講義 火薬学 |
科学技術者倫理 総合環境理工学セミナー 外国文献講読 卒業課題研究 |
総合環境理工学セミナー 外国文献講読 卒業課題研究 |
卒業課題研究 | 卒業課題研究 | |
JABEE認定について
旧土木環境工学科では、日本技術者教育認定機構(JABEE)による土木環境工学プログラムの認定を受けました。これは、大学などの高等教育機関で実施されている技術者教育プログラムが、社会の要求水準を満たしているかどうかを審査・認定するものです。審査の結果、2004年度からの認定がなされ、本コースの教育プログラムやプログラム修了生が社会の要求する水準を満たしていることが保証されました。JABEE認定の対象者は、2004~2020年度卒業生であり今後も継続受審予定です。なお、JABEE認定プログラムの修了生は、国家資格である技術士の試験において、一次試験が免除されるという特典があります。なお、社会基盤コースにおいても、このJABEE認定を継続する予定です。
学習・教育到達目標
|
No.
|
主文 |
No.
|
項目 |
キーワード
|
|---|---|---|---|---|
|
(A)
|
社会基盤整備において、人間の幸福や公共の福祉、地球環境的視点から、社会の要請を多面的にとらえ、 確固とした土木環境工学の基礎的および専門的知識や技術を用いて、総合的な解決策をデザインする素養と能力を身につける。 |
(A-1)
|
土木環境工学の基礎知識 |
基礎知識
|
|
(A-2)
|
土木環境工学の応用知識 |
応用知識
|
||
|
(A-3)
|
社会基盤整備における総合的な解決策のデザイン能力 |
総合解決能力
|
||
|
(B)
|
自然や生命等、地球環境に広く関心を持ち、これを多面的な視点で考察する能力、ならびに土木環境工学に関する基礎知識の応用を通じて、自然と社会との関わりやそれら相互の影響を理解し、技術者として自然や社会に対する責任を自覚する素養を身につける。 |
(B-1)
|
地球環境に関心を持ち多面的な視点で考察する能力 |
地球環境
|
|
(B-2)
|
技術者としての倫理観 |
論理間
|
||
|
(C)
|
社会がかかえる課題の進化を認識し、土木環境工学において新たに生じる課題対応に必要な専門的知識や技術を、自主的、継続的に学習できる能力を身につける。 |
(C-1)
|
新たな課題に対応できるよう自主的・継続的に学習する能力 |
継続的学習
|
|
(D)
|
数学や自然科学、情報技術などの基礎知識を習得し、自然現象や社会現象のメカニズムを理解する能力を身につける。また、人文科学や社会科学の知識を習得することで、多様な情報を収集・分析し、社会の要請を多面的にとらえる能力を身につける。 |
(D-1)
|
自然科学などの基礎知識 |
自然科学
|
|
(D-2)
|
人文科学および社会科学知識 |
人文・社会
|
||
|
(D-3)
|
情報を収集・分析する能力 |
情報
|
||
|
(E)
|
現象を理解し、問題の所在・解決策を論理的に記述・発表する能力を身につける。また、討論を通じて現象に対する理解を深め、解決策の問題点を改善する能力を身につける。さらに、国際的に通用するコミュニケーション基礎能力を身につける。 |
(E-1)
|
論理的に記述・発表する能力 |
記述・発表
|
|
(E-2)
|
討論を通じて改善する能力 |
ディベート
|
||
|
(E-3)
|
国際的コミュニケーションのための基礎能力 |
コミュニケーション
|
||
|
(F)
|
自然環境、社会環境、経済環境、時間等の制約下において、目標とそこに至るプロセスを自ら設定し、計画的に仕事を遂行する能力を身につける。 |
(F-1)
|
目標とプロセスの設定能力 |
立案
|
|
(F-2)
|
計画的な仕事の遂行能力 |
遂行
|