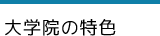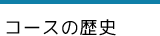土木技術とコースの紹介
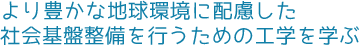
社会基盤コースでは、自然環境・社会環境に配慮した社会基盤の整備・維持・管理や安全・快適・な地域環境の創造・保全についての教育研究を行います。構造力学、建設材料学、水理学、交通システム計画などを中心として、安全・安心・快適な地域環境を創造・保全する技術について学びます。

![]()
土木技術は「自然の偉大な力の源泉を人類に役立たせるための技術」といわれています。公共施設の建設を通して、安全で快適な環境の創造により人間の生活環境の向上に貢献してきました。しかし、社会資本を整備するために現在の豊かな自然環境を破壊してよいとは限りません。社会基盤コースでは5つの基礎的な分野における研究と教育をベースとして、災害に強く快適である持続可能な社会基盤の整備のあり方について学んでいきます。
![]()
以下の知識と能力を備えた技術者の育成を目指しています。
(1)福祉をめざした快適な都市・地域社会の創造に関する知識と能力を備えている
(2)環境に適合した構造物の設計と施工に関する知識と能力を備えている
(3)水環境と地盤環境の保全、改善に関する知識と能力を備えている
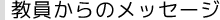
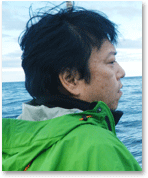
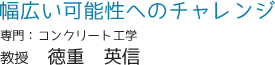
土木は有史以来、ひとが安全で快適に便利に生活するための「基盤」を造り、そしてそれを守るための学問であり、そしてそれを応用する技術でもあります。皆さんが普段何気なく生活しているときは勿論のこと、ひとたび災害が起きればそこから一刻もはやく復旧・復興して、安心して生活するためのハードとソフトが必要です。この基礎となるのが「土木」です。ひとが生きていくためには、個人であれ組織であれ様々な問題を解決していかくてはなりません。この問題解決能力を養うためには、「机上」と「現場」の両者が味わえる「土木」の世界はとても魅力があると思います。土木は工学の全ての技術と関連しますし、地球物理を始めとした理学とも関連が深い学問です。幅広い可能性にチャレンジしてみませんか?

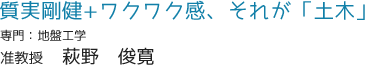
みなさん「土木」というとどんなものを思い浮かべますか?土木は道路や橋梁、鉄道といった社会インフラを支えている質実剛健な学問ですから、そのイメージは少々お堅いかもしれません。…確かに。土木工学は堅実で、社会に広く必要とされていて就職も安定している、そんな学問分野といえるでしょう。でもそれだけじゃないんですよ。私の専門は地盤工学なんですが、そういった研究の一方で、近い将来の月面でのインフラ開発を見据えて月地盤の性質を推定するという、一見浮き世離れした研究もおこなっています。どうですか、ちょっとワクワクしませんか?質実剛健+ワクワク感、それが土木工学なんです。みなさんも一緒に「土木」してみませんか?

安心・安全な未来を築く
熊谷 爽騎さん(秋田県出身)
*メッセージは2025年3月時点のものです